平成という時代はみなさんにとってどんな時代でしたか?
平成は30年と113日間で、2019年(平成31年)4月30日までが平成でした。
みなさんは平成にどんなカレーが流行ったのか覚えていますか?
今回は、平成で起こったカレーにまつわる出来事を解説します。
タイカレーが人気になる
昭和の末期バブル景気といって空前の好景気状態のころ。
1986年(昭和61年)~1991年(平成3年)です。
海外旅行に出かける人が増えて、ちょうどその頃エスニック料理がブームになります。
エスニックとは「民族的な」という意味で、特に東南アジアの料理をエスニック料理と呼ぶことが多いです。
エスニック料理ブームの火付け役がタイ料理。
1990年(平成2年)タイカレーが人気になります。

特にタイのカレーは、日本のカレーやインドカレーとは違っていました。
タイカレーはココナッツミルクの入ったカレーなのです。
タイカレーは東南アジアで食べられているスパイシーなスープカレーで、辛さと甘さがミックスされていて病みつきになる味が魅力。
タイカレーはハーブや発酵調味料をたくさん使っているインドカレーとは違います。
ココナッツミルクの他にもトウガラシやパクチー、シナモン、ターメリックなどのスパイスに
ナンプラーが入っています。
また、日本のカレーのようにドロッとしたルウではなくさらっとしたスープ。
タイカレーには、
- グリーンカレー
- イエローカレー
- レッドカレー
の3種類あります。
「グリーンカレー」と「レッドカレー」に使われている材料は基本的に同じです。
カレーに使うトウガラシによって違いがあります。
レッドカレーは、赤トウガラシ。
グリーンカレーは、青トウガラシ。
ちなみに辛さの順番は次のとおり。
- グリーンカレー(辛い)
- レッドカレー
- イエローカレー(辛さ控えめ)

余談なんやけど、1993年に「平成の大凶作」と言われる日本のお米が不足したんや。
タイ米も緊急輸入されたんやで。
カレーが宇宙へ行く!?
1992年(平成4年)になんとカレーが宇宙に行くんです!
宇宙に初めてカレーを持ち込み&食べたのは、NASA毛利衛(もうり まもる)さん。
毛利衛さんは日本人で初めてスペースシャトルで宇宙へ行った方です。
「エンデバー号」日本人科学者として搭乗。
毛利さんと同乗していたクルーにもカレーが好評だったとか。

1969年(昭和44年)に打ち上げられたアポロ11号の宇宙食から、すでにレトルトパウチ食品が使われていてたんやて。
無重力空間なので、お皿の上でご飯とカレーを食べることはできません。
レトルトカレーの封を切ってその中にご飯をいれて、カレールウに浸して食べるスタイルでした。
この食べ方に異を唱えたのは元宇宙飛行士の土井隆雄(どい たかお)さん。
カレーライスはカレーとご飯が一緒に盛り付けていなければならない
NATIONAL GEOGRAPHIC HP マガジンより
土井隆雄さんは宇宙でもカレーの食べ方にもこだわったとか。
1997年(平成9年)スペースシャトル コロンビア号に搭乗した時に、特製パックを作り、カレーとライスを一緒に盛り付けてスプーンで食べたそうです。
土井隆雄さんは、日本人初めて船外活動を行った方なんですよ。
「カレーの街よこすか」誕生
「横須賀(神奈川県)とカレー」とどんな繋がりがあるのでしょうか?
時代はさかのぼり、明治時代のこと。
旧日本海軍と陸軍には頭を悩ませていることがありました。
海軍と陸軍に病死で亡くなる軍人が多かったんです。
病死の原因はたんぱく質やビタミンB1が不足で起こる脚気(かっけ)。
その頃主食は白米ですが、副食が貧相でした。
海軍の軍医高木兼寛(たかき かねひろ)さんが「兵食改革」に取り掛かります。
イギリス海軍を見習ってカレー風味のシチューに小麦粉でとろみをつけます。
それをご飯にかけたものを取り入れました。
この時に採用されたカレーが日本のカレーライスの元祖とされています。
旧日本海軍の鎮守府(ちんじゅふ)の一つが横須賀。
鎮守府とは、軍港の置かれた海軍の拠点のことです。
カレーライスが一般家庭に普及したきっかけとなったのが旧日本海軍とされています。
兵役を終えて故郷へ戻った兵士たちによって日本全国広まったんだとか。

カレーと横須賀が繋がったね!
1999年(平成11年)横須賀市は「カレーの街宣言」をし、カレーの街よこすか推進委員会が
設立されました。

1998年(平成10年)、海上自衛隊地方総監が退任前のお別れパーティでのこと。
「海軍ゆかりの地である横須賀をカレーの発信地にしてみては?」という言葉がきっかけのようだよ。
その言葉を受けて横須賀市役所、横須賀商工会議所、海上自衛隊が協力したんだって。
明治41年「海軍割烹術参考書」のレシピをもとに現代風にアレンジしたカレーが「よこすか海軍カレー」です。
またよこすか海軍カレーにはルールがあります。
- 肉は牛肉か鶏肉を使うこと
- 人参、玉ねぎ、じゃがいもが入っていること
- カレー粉、塩、小麦粉を使うこと
- 漬物(チャツネなど)、サラダと牛乳を必ず添えること
1999年(平成11年)8月に第1回よこすかカレーフェスティバルを開催。
日本初のカレーフェスで、カレーで街おこしのモデルとなりました。
日本初カレーのアミューズメント施設
2001年(平成13年)横浜市中区伊勢佐木町に「横濱カレーミュージアム」がオープンします!
全国にある有名&個性的なカレー専門店を集めたフードテーマパークです。

横濱カレーミュージアムは、年中無休で入館無料だったんや。
飲食店の他にカレーミュージアムオリジナルのグッズもあり、全国各地のレトルトカレーも
取りそろえていました。

2006年(平成18年)11月末で累計来館者数は約870万人だって!
2007年ごろ出店していたお店はこちら。
- トプカ(東京・印度&欧風カレー)
- レーベン(東京・欧風カレー)
- 湘南カレー紅(湘南・欧風カレー)
- パク森(東京・オリジナルカレー)
- 伽喱本舗(博多・焼きカレー)
- 琉球カレー(沖縄カレー)
- Kingデリー(東京・インドパキスタンカレー)
- 木多郎(札幌・スープカレー)
- 横濱フレンチカレーの店(横浜・フレンチカレー)
- アジアンランチ(東京・アジアカレー)
- 讃岐五右衛門(香川・カレーうどん)
- 船場カリー(大阪・欧風カレー) ※横濱カレーミュージアムHPより
カレー屋 パク森は2001年の開館から閉館までお店を構えていたそうです。 (現在の店名:カレー屋パクパクもりもり)
横濱カレーミュージアムは開館をきっかけに全国のカレー専門店が知られるようになり、カレー専門店ブームにもなりました。
残念なことに、2007年(平成19年)3月31日に横濱カレーミュージアムは、事業期間満了に伴い閉館しました。
北海道発祥「スープカレー」が全国へ
2002年(平成14年)~2006年(平成18年)頃にかけて北海道発祥の「スープカレー」が
ブームになります。

スープカレーは、スパイスが効いたスープと大ぶりの具(肉・野菜)が特徴です。
スープカレーの元祖と言われているのが薬膳カリィ本舗アジャンタ。
1975年(昭和50年)創業で、薬膳カリィがスープカレーの原型と言われています。
漢方の養生食とインド料理を融合したものです。
「スープカレー」という名前で売り出したのが、1993年(平成5年)に開業したスパイスマジックというカレー店。
2003年(平成15年)にスパイスマジックが、横浜カレーミュージアムに出店をきっかけに
スープカレーブームに一役買いました。
カレーうどんブーム
2003年(平成15年)はカレーうどんブーム。

前年度の讃岐うどんブームに乗って、ちょうどカレーうどん誕生100周年でもあり、イベントや雑誌の特集を組まれました。

カレーうどん発祥店は三朝庵さんやね。
1983年(昭和58年)創業、クリーミーカレーうどんの「古奈屋」を中心にマイルドな辛さのうどん店が女性に支持されたのも、この時期です。
カレーうどんチェーン店や専門店も生まれ、独創性のあるカレーうどんがお目見えしました。
フレンチカレーブーム
2005年(平成17年)にフレンチカレーブームがやってきました。
横浜観光プロモーションフォーラム認定事業の一環として、横浜ご当地カレー「ハマカレー」のイベントを行うことに。
仏蘭西料理亭 横濱元町の「霧笛楼」今平茂総料理長を主料理人や料理研究家などで構成された「ハマカレー制作委員会」を結成。
創作プロジェクトのイベント実施され、横浜フランスカレーを創り出しました。
横浜フランスカレーのコンセプトは、
- おしゃれでハイセンスな横浜らしさを感じられるカレー
- フランス料理の技法を利用した気品と繊細さのあるカレー
フランス料理のソース技法を活かした上品なカレーで、おしゃれさと繊細な味が女性に人気だったそうです。
今でも、霧笛楼にて横濱フランスカレーが食べられますよ。(数量限定)
国産牛肉を使用した欧風カレーです。
白カレー&黒カレーブーム
2006年(平成18年)白カレー黒カレーブームがやってきました。

白色と黒色のカレーのブームが同時に来たんやね。
・白カレー
ホワイトカレー(白カレー)は、帯広市のカレー店「カレーリーフ」が元祖です。
なぜカレーが白いかというと、クリームソースベースでウコンまたはターメリックを減らしたから。
見た目はシチューのように薄黄色ですが、味はスパイスの効いたカレーなんです。
その名も「フランス風カレー」。
またブームと同時期にハウス食品より白いカレールウ「北海道ホワイトカレー」も発売しました。

またご当地グルメとして、北海道紋別市の「オホーツク紋別ホワイトカレー」。
2007年(平成19年)「北海道じゃらん」の編集長が提案して実現した企画です。
オホーツク紋別カレーには定義があります。
- 名称はオホーツク紋別ホワイトカレーとすること
- オホーツク紋別をイメージしたホワイトカレーにすること (紋別のイメージ:流氷のまち・漁業のまち・農業酪農のまち)
- 紋別産の帆立や牛乳を使うこと
- なるべく旬のものをつかうこと
- 北海道産の白米の上に具材をのせて、ルウは別添えること
- ガリンコ号Ⅱをイメージした食材を使用すること ※ガリンコ号Ⅱとは砕氷船(さいひょうせん)
- 円形の皿で提供すること
- はまなすチャツネを付けること
- ガリンコ号Ⅱ、ホタテ、アザラシをプリントした共通のスプーン袋を装着すること
- 1000円以下で提供すること(現在は食材費高騰で1000円以上になっている)
・黒カレー
黒カレーのブームの背景には、ちょうど黒色の食品(黒豆・黒ゴマ、黒米など)を取り入れるという健康ブームが重なったとか。
ブラックカレー(黒カレー)は三重県津市の東洋軒が発祥で、昭和の初めに考案されました。
(詳しい年号不明)
初代料理長の猪俣重勝(いのまたしげかつ)さんが考案したブラックカレー。
フラックカレーが誕生したのは陶芸家の川喜田半泥子(かわきた はんでいし)氏がきっかけ。

「東の北大路魯山人・西の川喜田半泥子」と称される陶芸家であり食通やで!
ある日川喜田氏は「黒いカレーができないか」という猪俣さんに持ち掛けます。
半泥子が東京で食べた濃い色のカレーが忘れられなかったそうですよ。
最高級の松坂牛脂と小麦粉をお店秘伝のスパイスを丁寧にじっくり炒めた黒いルー。
黒いカレーは、スパイスを炒ること黒いカレー粉ができます。
2006年(平成18年)にカラメルソースが入ったカレーやイカ墨を使用した黒カレー(船場カリー)が登場。
ホワイト(白)カレー同様ブラック(黒)カレーもに大きな注目を集めます。
- 1990年(平成2年)タイカレーブーム
- 1992年(平成4年)カレーが宇宙食になるへ
- 1999年(平成11年)「カレーの街よこすか」が誕生
- 2001年(平成13年)日本初カレーのアミューズメント施設「横濱カレーミュージアム」がオープン
- 2003年(平成15年)カレーうどんブーム
- 2004年(平成16年)スープカレーブーム
- 2005年(平成17年)フレンチカレーブーム
- 2006年(平成18年)白カレー黒カレーブーム
毎年と言っていいほどカレーブームはやってきていたんですね。
調べて初めて知りました。
次回は2007年(平成19年)以降のカレーの出来事を解説します!


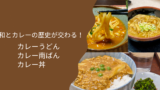


コメント